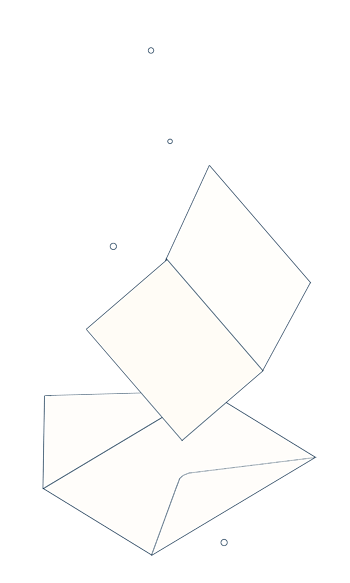Catch Me If You Can ! (from K)
学校の小型焼却炉に、遺品を放りこんだのは瞠だった。
ダイオキシンを発生させない優秀な焼却炉は、1000度以上の高熱で何もかもを燃やした。
手を入れようとする槙原を、瞠は必死に押し留めたという。
古川の遺品だと、瞠が知っていたのかはわからない。その後、槙原から聞いた恐ろしい話を知っていたのかも。
――槙原は人間不信の寸前だった。
「賢太郎のことを褒めてたんだ。賢太郎のことを面白い奴だって言ってたから……」
俺の膝にすがりながら、咲は声を震わせた。
槙原の来訪から数日後、俺は咲の部屋にいた。変わらず散らかった部屋で、咲は俺の顔を見るなり、整った顔を歪めた。
「眞みたいな人だと思った。眞じゃない、賢太郎の友達が欲しかった。僕だけが知ってる、賢太郎の友達だ。楽しいことだと思ってた」
咲は寂しかったのだ。咲の寂しさに誰も気づかなかった。
溺愛する姉を失った咲は、何よりも自分を愛する存在がいない世界を、初めて歩いていたのに。
激しい愛情は麻薬だ。恐ろしさと快楽を与える。
求められることに慣れていた咲は、姉に背を向けられて、宙ぶらりんに浮かんでいた。彼が覚悟していたことだとしても。
決意するのは簡単だ。
だが、決意を日常するまでに、地獄の苦痛を味わう。
ごめんなさい――咲は声を震わせた。
「河邊さんは全部知ってるって言ったんだ。僕らが貴方を監禁したこと」
咲の頭を抱きながら、俺は怒りに身を震わせた。
同僚の河邊が仕入れたスクープは、現在、証拠集めに入っている。何も出て来なければ、未成年の証言だけだ。記事にはならない。
だが、もしも、世間に公表されることになれば、彼らは罪に問われ、社会の好奇の目を浴びて、人生を壊されるだろう。
現役小説家、代議士の息子、元芸能人の犯罪被害者――
話題には事欠かない子供たちだ。
「どうしよう、賢太郎。みんなが守ってきた秘密なのに……」
「……大丈夫だ」
勝算などなかった。咲の頭を撫でて、俺は繰り返す。
「大丈夫だ」
嘘を吐いているつもりはなかった。
俺たちは強く、逞しい。ここまでの日々を乗り越えてきた。
――揺り返しが来るんだよ。
幸福までの道程だ。一歩、一歩、慎重に足を進めて行く。
一瞬で変わる季節がないように、枯れ葉の落ちる道から、凍えた大地へ。そして、柔らかい芽の膨らむ草原へと。
いくつもの試練に、試されながら。
「父親が子供を認知するためには、乳児の時は母親の承諾、成人後は本人の承諾が必要らしい」
咲の部屋を出た後、俺は隣室の煉慈に招かれた。
咲が秘密を漏らしたことを、子供たちはまだ誰も知らない。煉慈の要件は別のことだった。
彼の父親の隠し子――彼の兄の問題だ。
「相続の問題もあるし、親父は誠二を認知したがってる。そこで、誠二が出した条件が、大澤誠二の死の真相を公表することだ」
万年筆の蓋を丁寧に閉めて、煉慈は回転椅子の上で手を組んだ。
「神波京子を孕ませたための自殺ではなく、親父らを助けようとして凍死したと」
「個人の名誉を回復させたいと言うことか」
「どうかな。たぶん、誠二は試してるんだと思う。親父らには出来ないと思ってるんだろう」
煉慈は嘆息した。
父親に信を置かれたことが、煉慈の自信に繋がっているのだろう。すぐに疳癪を起した、気難しい少年の影は薄れている。
「親父は公表すると言った。俺もそれでいいと思う」
「……30年前の出来事だ。法的な罪には問われないだろうが、不要な醜聞を招くぞ。だいたい、どうやって公表する。おもむろに教壇で語り始めるのか。暴露本でも出すのか」
「おまえがいるだろう」
俺は目を見開いた。
背筋が冷たくなった。
「白峰や茅の親父には、今確認を取っている。和泉の親は故人だし、名前は明かさないつもりだ」
「……何が起こるのかわかってるのか」
「覚悟はしてるさ」
「覚悟!? おまえも親父もわかっていないだけだ! 古川の末路や、春人の苦悩を見て来ただろう!?」
俺が声を荒げると、煉慈は驚いた顔をした。
性根の幼い彼は、善意や好意が、必ず良い結果を結ぶと思っている。自分がそれを経験し、学んできたからだ。
だが、他人や世間はそう単純じゃない。俺は首を振って、煉慈の肩を押さえた。
「いいか、煉慈。記事になれば、おまえや親父を知らない人間が、数行の文字でおまえたちの人格を決める。おまえの評判にも付いて歩くだろう。一度世に出したら、決して取り戻せないんだ」
「親父もわかってるさ。だが、過去のことを後悔してるんだ」
「それこそ、神父に懺悔でもして来い! おまえが思う以上に、世間には意地汚い好奇や、説教面の悪意が溢れている。おまえたちを理解する前に、奴らはもっともらしい批判をする。俺もそうだった、知ってるだろう?」
「……おまえは後悔してるんだろう?」
「そう言う話じゃない。わかってくれ。おまえは著名人だ。大衆は著名人の転落を何より喜ぶ。予言してもいいが、咲や瞠より、晃弘や春人の名が紙面に飛び交うだろう。そのことは考えているのか?」
「あいつらもわかってくれるさ。白峰の親父はいい奴なんだ。茅の親父は、少しくらい痛い目に会えばいい。みんな、そう言ってる」
「煉慈……。煉慈、目を覚ましてくれ。頼むから」
「親父はやりなおそうとしてるんだ。俺も親父に協力したい。……親父とやり直したい。信用できる記者は、おまえしかいないんだ」
「古川にしたことと同じことを、おまえたちにしろというのか!? どういう結果になるか、わかっているのに!」
学習机を殴り付けて、俺は怒鳴った。
昂った呼吸を必死に落ち着かせて、手のひらで顔を覆う。
「……頼むから、俺にそんなことはさせないでくれ」
30年前の事件を公表することで、俺の監禁事件についての情報も、漏洩していくかもしれない。
未成年だとは言え、こいつらは監禁、清史郎は死体遺棄の罪に問われる。子供たちは法に裁かれるべきなのか。隠匿はやはり間違いなのか。
槙原はどう思ってるんだ。
保留にしてくれと、俺は煉慈に伝えた。別れ際に煉慈は言った。
「もうすぐ夏休みなんだよ」
「だから、なんだ」
「清史郎が休学してから一年が経つ。俺たちと卒業できないことはわかっていたが、このままだと復学も難しくなるぞ」
「…………」
「連れて来てくれよ。あいつを」
俺は不思議な気持ちになった。
あれほど学校の似合う子供はいないのに、清史郎はそんな長い間、学校を離れていたのか。
あいつは何を見て、何を考えているんだろう。
真夜中に人の気配がした。
どこから入ったのか、清史郎が俺を見下ろしていた。犬はいない。
「……よう」
掠れた声で、俺は寝返りを打った。Tシャツを確認して、落書きがないことを確かめる。部屋も風船で埋まっていない。
「おかえり」
「ただいま。電気付けてもいい?」
俺は頷いた。とことこと清史郎が歩いて、部屋の電気を付ける。
眩しさに目を顰めながら、弟の姿を確認した。今までどこにいたのか、清史郎の肌は真っ黒に焼けていた。
「……犬はどうした?」
「賢太郎」
「そいつはどうした」
「これから助けに行く」
「………?」
肩の後ろを掻きながら、ゆっくりと身を起こす。寝台の傍らに座って、清史郎は俺と目の高さを合わせた。
しゃがんだ姿勢のまま、膝の上で、頬杖をついている
「兄ちゃん」
「なんだ」
「俺が死んだ時泣いた?」
「そりゃあな」
「俺がもし、死にそうな目に会ったら、助けてくれる?」
頷きかけた俺は、嫌な予感がした。
愛情を確かめる響きではなく、具体的な真剣味があったからだ。
「そこに座れ」
「ちょっと忙しいし……」
「いいから座れ。どこに行ってた。ちゃんと説明しろ」
「先に俺が聞いたんじゃん。答えてよ」
「助けるさ」
寝台の上に胡坐をかいて、俺は清史郎を見つめた。
瞬きを繰り返すうちに、眩しさに目が慣れていく。物語の続きをねだるように、清史郎は目を輝かせていた。
この顔に弱かったことを思い出す。
「おまえがどんな奴になろうと、どこにいようと、人に迷惑を掛けない限り、おまえの味方になってやる」
「スーパーマンみたく、ピンチの時にかけつけて?」
「そこまでの速度は期待するな。だから、何をしているかちゃんと説明しろ」
俺は息を吐いて、清史郎の頭に手を置いた。
「誰かにおまえのことを聞かれた時――迷わずに、あいつはいい奴だと答えたいんだよ」
清史郎は頬をゆるめた。
俺の手に懐くように、ぐりぐりと頭を押し付ける。
「俺もだよ、兄ちゃん」
その言葉が全てを解決した。
たけのこが生えるように、ぐんっと清史郎は立ちあがった。健康的な浅黒い肌は、どこか精悍さを弟に与えている。
俺に似た、いい男だ。
「島に行く」
「島?」
「うん。幽霊島っていうところ。賢太郎もそこにいる」
「一人で行くのか」
「誠二を連れて行く。鉄平の責任を取らせて、根性曲がりを叩き直す」
「古川に関係のあることなのか……?」
きょとんとした顔で、清史郎は首を振った。
「ないよ。俺の友達をあいつは殺した。だから、俺の友達のために命を張らせる」
「清史郎。俺が言った言葉を覚えてるか。ついさっきだ」
「俺が死んだ時、兄ちゃんが泣いた」
「違う。人に迷惑を掛けるなと……」
にやりと笑って、清史郎は俺に飛びついた。
勢いが余って、ごんと俺の後頭部が壁に当たる。5歳の時より強い力で、17歳の腕いっぱいに、清史郎は俺を抱き締めた。
気恥かしさと、懐かしさを、少年の体と一緒に抱く。
清史郎からは、太陽と埃の匂いがした。
「迷惑なんて掛けない。俺は知ってるんだ。みんなが俺をほっとかないこと。俺を助けてくれること」
小悪魔め――俺は肩を竦めた。
「兄ちゃんも、幽霊棟のみんなも、槙原先生も、俺のピンチを助けるよ。一致団結って奴をして、ヒーローみたいに活躍する。誠二にもそれが出来たら、許してやる」
清史郎は無邪気に、そして力強く、声を弾ませた。
かなわないな、と笑った。愛していることがバレている。どうしようもない、この弟を。
「清史郎」
弟の髪を撫でて、俺は笑った。
「必ず、俺を呼べよ」
清史郎は素直に頷いた。元気よく笑いながら、俺の口をこじ開けて、錠剤を放りこんだ。
舌の上に苦みが広がる。
驚愕するより早く、清史郎は両手で、俺の口を塞いだ。
「………!?」
「ごめん。本当は寝てて欲しかったんだ。この部屋で内緒でしたいことがあって」
「……! ……!」
「大丈夫! 前もこっそり水に入れたから! 兄ちゃんもう飲んでんから! 全然大丈夫!」
俺は額に青筋を浮かべた。
人に迷惑をかけるなといった意味を、このガキは全然わかっていない。
「痛い痛い痛い! ハゲる! 兄ちゃん、ハゲる!」
全力で髪を引っ張り、どてっ腹を蹴り付けているうちに、意識が薄れていった。白くかすむ視界の中、清史郎が額の汗を拭っている。
「うおー、危ねえ……」
その言葉を最後に、俺は意識を失った。
翌日、テーブルの上にはICレコーダーと、写真と、スーツケースがあった。ICレコーダーには河邊と咲の声が入っている。写真にはデスクの奥さんと河邊がホテルに入って行く光景が写されていた。
スーツケースは馬鹿みたいに重かった。中味を確認して、俺は気を失いそうになる。
中味は金塊だった。1キロ単位の金塊が100個近く詰まっている。震える手で、同封されていた手紙を確認すると、こう書かれていた。
『幽霊島の隠し財産です。うまいこと隠しておいてください』
兄弟の縁を切りたい、と本気で思った。
――あれから、1ヶ月後。
8月の半ばに、清史郎から手紙が来た。
俺にだけじゃない。幽霊棟の学生たちにも、槙原にも。
それは招待状だった。
『俺がお世話になっている島の裏神事に招待します。
お祭りのようなものです。
怪我をしてる人と女の人には、触らないようにしてください。
島に来る7日前から。よろしくです』